令和7年度4年セミナーの案内(日比野)
ゼミとは
数学のゼミは
基本的に,数学の専門書の輪読です。
つまり,当番になった学生がテキストを勉強しその内容を講義するものです。
簡単に言えば,
先生の代わりをする
と思っていただいて結構です。
私は物分りの悪い生徒の役をします。
なにかにつけ,
すぐに「それはどうしてですか」
「どういう定理を使ったのですか」
「証明を教えて下さい」
「その公式を使えるのはどういうときですか」
「今の場合はその公式を使えるのですか」
などと質問します。
担当者はそういう(意地悪な?)質問にも答えられるように
『完全に全部わかった』という状態になるまで
――少なくとも,そういう気持ちになるまで――
十分に勉強してください。
そのとき,他の本を調べたり,人に聞いたりしても構いません。
むしろ,そうしてください。
使用テキストについて
当ゼミでは原則として,洋書の数学の専門書を読みます。
外国語の本を読むのは,日本語の本だとただ朗読していても
正しいことを言っているので,
学生が理解していないのにそのままスルーしてしまうのを防ぐためです。
洋書なら,日本語に訳した時点で間違っていれば,
それは数学が理解できていないことの証左になるし,
訳せないときにも数学の内容から推測することで,
より数学の理解が進むという教育的効果もあります。
ただ,最近は翻訳ソフトが進化してきたので,
外国語を訳すことの意味が無くなってきました。
来年度はとりあえず以下のテキストを候補にしています。
- R. Courant;
Dirichlet's Principle, Conformal Mapping, and Minimal Surfaces,
Dover Pub.(2013)(first published in 1950)
変分法のディリクレの原理に関する古典の本です。
- S.Abbott;
Understanding analysis,
Springer (2015)[PDF]
微積分の基礎的な本です。
2年生の「解析学基礎I」の発展を英語の教科書で読むと思えばよいでしょう。
-
M. Gardner;
Sphere Packing, Lewis Carrol, and Reversi,
Cambridge Univ. Press (2009)
有名なガードナーの数理パズルの本で面白そうですが,
数学のゼミとして成立するか微妙です。
-
P. Billingsley;
Probability and Measure,
A Wiley-Interscience Pub.(3版1995)[PDF]
私の専門が確率論だと知ってて
このゼミを希望する人は,
確率論をやりたいのだと思うので一応この本も候補に入れておきます。
候補テキストは
日比野研究室に置いてありますので,
見たい人はいつでも訪ねてきてください。
これらに限らず, 他に読みたい本のリクエストが学生の方からあれば それにも応じます。
ゼミの進め方
参加者の都合に合わせて曜日を決めますが,
終了時間は特に定めず
その日の担当者が担当した分を終えるまで続けます。
時間が長いので体力勝負な感じですが,
担当者以外はただただ終わるのに付き合わされている
という雰囲気になってしまって
自分の担当するところ以外は全く理解していない,
という状態になってしまわないようにしてください。
プレゼミ
上述の悪い状況を産み出さないためにも,
ゼミの前に
学生同士でプレゼミ(リハーサル)を行うことを勧めます。
友達と協力し合って勉強するのもいいものです。
また,先生の視点で友人の発表のアラ探しをすることは
良い勉強にもなります。
その他
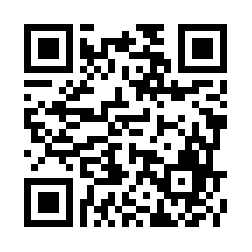 ゼミの受講人数には制限があります。学生同士で適当に調節して下さい。
ゼミの受講人数には制限があります。学生同士で適当に調節して下さい。
私が研究室にいるときは
いつでも訪ねてきて結構です。
が,
いつも研究室にいるとは限りません。予約してから訪ねるのが良いでしょう。
以上のことを
納得した上でゼミを受講して下さい。
2025年度は,当ゼミには修士1年と修士2年が1名ずつ在籍します。
ゼミの雰囲気について彼らに相談してみるのもよいでしょう。
私のHPの過去のゼミの記録
には,今までのゼミの様子や感想などを書いているので,参考にしてください。
右のQRコードからも行けます。
日比野雄嗣 hibinoy@cc.saga-u.ac.jp
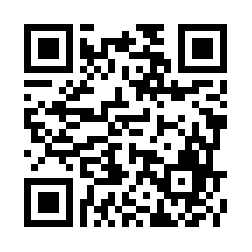 ゼミの受講人数には制限があります。学生同士で適当に調節して下さい。
ゼミの受講人数には制限があります。学生同士で適当に調節して下さい。