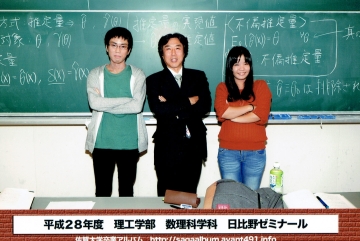日比野ゼミ
ここには4年生のゼミ(数学講究)について書いています。
※本文中の表現は書かれた年代・書かれた状況を考慮し、当時のまま掲載しています。

 これは僕が初めて担当したゼミなので
特に印象に残っています。
この学年が1年生のとき
僕がフレッシュマンセミナーを担当したためか,
あらかじめ何人かの学生が僕のゼミを希望しているという噂を聞いていました。
「先生のゼミに希望者が殺到して
受けられなくなるのがいやだから,
ゼミ案内のときに人が来ないように紹介してください。」
なんて言い出す学生までいる始末。
ところが
実際には希望者は
4人だけでした。
しかし,
ゼミをするにはこれくらいの人数がちょうどよいです。
これは僕が初めて担当したゼミなので
特に印象に残っています。
この学年が1年生のとき
僕がフレッシュマンセミナーを担当したためか,
あらかじめ何人かの学生が僕のゼミを希望しているという噂を聞いていました。
「先生のゼミに希望者が殺到して
受けられなくなるのがいやだから,
ゼミ案内のときに人が来ないように紹介してください。」
なんて言い出す学生までいる始末。
ところが
実際には希望者は
4人だけでした。
しかし,
ゼミをするにはこれくらいの人数がちょうどよいです。
読んだ本は
E.Artin; Gamma function
Holt Rinehart & Winston (1964) でした。
この本は僕が学生時代に図書室を徘徊していたとき,
異様に薄い本を見つけ,
これなら最後まで読み通せるかもしれないと思って借りたことがあります。
全部で40ページしかありません。
読んでみると
大変読みやすく
記述も丁寧です。
実数変数の場合しか扱われていないので
大学初年級のレベルです。
ゼミでも数学の内容で学生が困ることはほとんどありませんでした。
(これはウチのゼミの学生が優秀であったせいかもしれません。
と
ちょっとヨイショして
)
しかーし
学生は英語が異常に弱い!
英語が読めなくて止まってしまうことがしょっちゅうでした。
「differential」を「違いの」とかいわれた日にゃ,
本を投げつけたくなりました。
さすがにいくら英語で止まってしまうといっても, 40ページは1年もかかりません。 仕方ないので 続きの本を探してみました。 佐賀大の数学図書室を徘徊してガンマ関数について書いてある本を 調べたのですが ほとんどの本がガンマ関数については 数ページ割いてあるだけです。 何ページも書かれている本はあっても このArtinの本の丸写しか, または 高度すぎて学部生には無理そうなものばかりでした。 結局 L.A.Lyusternik&A.R.Yanpol'skii; Mathematical Analysis pergamon press (1965) のChapter8を読むことにしました。 この本は途中の式をかなり飛ばした式変形が延々と続き, しかも その式を後で利用したりもしない というもので ようするに公式集のようなものでした。 しかし 学生にとっては途中の式変形をフォローするのが大変である反面, 理論的な流れを理解しなくてもついて行けるのが却ってやりやすかったようです。 ただし 形式的計算に理論的裏付けを与えることは, 学生にとってかなり意外なことであったようです。 もちろん Artinの本でもちゃんと一様収束を確認してから積分記号下で微分 とかしていたのですが それが全部書いてあるので, 意識することがなかったのでしょう。 最後の頃に学生から「難しくなってきた」と言われましたが, 上記のようにこの本は公式集なのですから 前半も後半も難しさは変わりません。 つまり 学生が理論的裏付けを与えなければならないことを意識してきたから 難しくなったように感じたわけで, こういう点での意識改革ができたのは 成果だったと思います。
就職に関しては 僕は特に何もしませんでしたが, 塾講師・ 地元の町役場・ 企業(佐賀電算センター)・ 私立高校教師に それぞれ無事に就職できました。 やっぱり ウチのゼミの学生は優秀であったかもしれません。 (と 最後にもヨイショ^^)

 前年度
学生が来ないように説明したのに4人きたので,
この年のゼミ案内でも同じように説明しました。
そうしたら
ナント4年生の希望者はゼロ!
学生がゼロなら
仕事しないですむだけなのでいいのですが
5人の学生が来ました。
彼らは留年生なのでゼミの説明会に参加していなかったのでした。
前年度
学生が来ないように説明したのに4人きたので,
この年のゼミ案内でも同じように説明しました。
そうしたら
ナント4年生の希望者はゼロ!
学生がゼロなら
仕事しないですむだけなのでいいのですが
5人の学生が来ました。
彼らは留年生なのでゼミの説明会に参加していなかったのでした。
使用した本は, F.Smithesis; Integral equations Cambridge Univ. Press. (1958) でした。 見た感じはわかりやすそうだったし, 「第2種Fredholm型は解けない場合があるが 第2種Volterra型は必ず解ける」 というのは 感動的(?)だろうと思って選んだのですが これが大失敗。 積分がLebesgueの意味なので この本は大学初年級ではありませんでした。 4年のゼミなのでLebesgue積分でもいいのですが, Lebesgue積分が分かっているようなら 留年なんかしないって。(^^)
最大の問題は 学生は何をしたらいいのか分かっていないことです。 僕がツッコミをいれると「そんなことまでしなくてはならないとは思ってなかった」 という反応がよくありました。 英語ができないのは相変わらずなので もう驚きもしないしショックも受けません。
この年は学生の都合(!)で午前10時から始めたのですが 昼には やめたいので,一人2時間と決めて, 1ページしか進まなくても2時間経ったら終わりで 翌週次の人に交代です。 だから 質問すると学生は黙ってしまい 時間が過ぎるのを待っています。 前年よりもメンバー間の仲は良かったようですが ゼミは非常に静かでした。 この方式は あまりよくないのかもしれません。
就職に関しては 何通かの推薦状を書きましたが, 2人は 東京のコンピュータ会社・ 佐賀の企業に それぞれ就職し, 1人は家業(漁業)を継ぐことになりました。
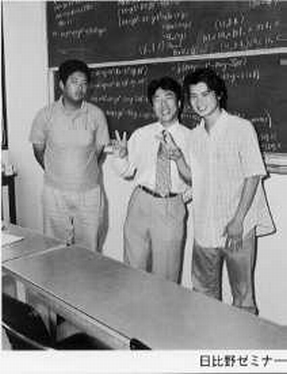
 久しぶりに4年ゼミを担当しましたが
この年の希望者はわずか2名。
久しぶりに4年ゼミを担当しましたが
この年の希望者はわずか2名。
しかも一人は留年生でしたので
当然2人は面識もなく,
盛り上がりに欠けるゼミになりました。
最初は
Paul R. Halmos; Introduction to Hilbert space and the theory of spectral multiplicity
Chelsea Pub. Co. New York
1951 (second edition 1957)
を読み始めたのですが,
この一人が異常に英語が弱い!!
すぐ上に「英語ができないのは相変わらずなので
もう驚きもしないしショックも受けません」と書いたばかりですが
彼の出来なさは特筆に価します。
真面目なのは確かです。
知らない単語を全部ノートに書き出して意味を書いていました。
しかし
それらの単語には
`on'やら`in'やら`is'まであるのです。
しかも
同じページの上のほうで調べたばかりの`on'をまた同じページで調べて書いていました。
`is'の意味には
「~は」と書いていたので,
辞書で調べたことを書いているわけでもないようです。
いくら単語をメモしても文法まではわからないようで,
前から訳していくので
of や if はいつも関係が逆になっていました。
この年は
前回の反省で
一人2ページと決めて,
それが終わるまでは何週でも同じ人がやり続ける方式にしたのですが,
彼の英語のせいでちっとも進まないので,
仕方なく
僕が全文和訳して渡しました。
もう一人は
普通…というよりは
優秀だったのでしょう。
結論から言うと
彼は
九州大学大学院に進学しました。
(そういえば
彼とは一緒に合コンに行ったりもしたな。(^^)
彼は
ゲノム情報解析に興味があるというので
後期からは
彼の読みたいのに合わせて
岩田茂樹・笠井琢美; 有限オートマトン入門(森北出版)1986
を読みました。
英語の出来ない方は
これ以上英語でいじめても仕方ないので
日本語で
Peter Frankl・前原潤; 幾何学の散歩道―離散・組合せ幾何入門―(共立出版)
の第2章を読みました。
要するに
2人しかいないのにゼミを2つ持ったわけで,
ゼミの大変さは
人数ではなく
学生のレベルにあると痛感した年でした。
彼は立命館大学の経済卒でして,
今だから言いますが
院試の成績はあまり良くなく,
判定会議で僕は不合格を主張したくらいなのですが,
『経済出身で数学の院に進もうとする意気込みを買う』ということで合格になったのでした。
で,若い人が指導しろということで
僕にお鉢が回ってきたわけです。
彼は
数理ファイナンスを勉強したいと決めてきていたので
(僕は数理ファイナンスを知りませんが)
テーマは最初から決まっていました。
まず 最初の半年は 数学のゼミがどういうものかを教えるために, 高木貞次; 解析概論(岩波書店)の第1章を読みました。 後に 彼は「最初の本を読んだときこれからどうなることかと思った。」 と語っていたので インパクトを与えることには成功したようです。 次に 福島正俊;確率論(裳華房)の第2-3章を読みましたが, ここまででM1が終わり 数理ファイナンスに全然触れていないことに焦りました。
そもそも 僕が経済学を知らないので 自分で勉強するのもままならず, 良いテキストを選ぶ自信もなかったので, M2からは 彼の好きな本で彼の好きなようにゼミをすることにしました。 このやり方はかなり乱暴で指導教官として投げやりな感じなので心配でしたが, ちゃんとまともに進んだのは やはり彼の努力のおかげでしょう。 彼は津野義道; ファイナンスの確率積分(共立出版)に沿って 進めていたようですが, 僕は沢木勝茂; ファイナンスの数理(朝倉出版)を見ながら聴いていました。 それで話が通じるのですから,この分野の基礎的内容はすでにfixされてきているようです。
ゼミの案内のところにも書いているように,
ゼミでは僕は‘物分りの悪い学生の役’として
細かいことをいろいろ質問するわけですが,
今回の場合は
教育的見地からの質問ではなく,
本当に分からなくて質問しているので,
説明がどんどん遡って行ってしまったりすることもあったし,
何ヶ月も前にやったことを
やっぱり良く理解できていなかったとか言って,
もう一度説明させたりもしたので,
単にテキストを読んでいくのとは
全然違う苦労をしたことでしょう。
最後に
英語を読む訓練で
A.Frieman; Stochastic differential equations and applications
Academic Press. (1975)を少し読ませましたが,
修論を見ると
他の英語の論文がいくつか参照されているので,
ゼミのために英語の論文を参考にして勉強したことがあったのでしょう。
このやり方はなかなか良いやり方だったかもしれません。
そう言えば
僕も修士のときのゼミは
参考にしていた論文はありましたが,
それに忠実に進めるわけではなく
話す順序を変えたり,
自分で証明をしなおしたりして,
適当に再構成してやっていました。
このやり方は一見大変そうですが
理解できない箇所があっても
そこを飛ばしてしまえばいいので
実は,
きっちりテキストに沿って進めるよりも気分的に楽なのです。
しかしそうは言っても
数学のゼミに慣れていないにもかかわらず,
このやり方でやり通した彼はよく頑張ったと思います。
さて
進路ですが,
彼は博士課程への進学を希望しました。
いくら頑張ったとは言っても
Lebesgue積分もやってないわけだし,
数学で博士に行くのは難しいのではないかと思ったら,
経済に進学したいとのことでした。
経済学者の知り合いは誰もいないので
指導してくれる人を自力で探すように,
と言って放っておいたのがまずかった。
彼が「誰も見つかりません」と言って泣きついてきたときには,
既にどこの大学も後期課程の二次募集が終わっていました。
慌てて八方手を尽くし――とは言っても数学者以外にツテが無いわけですが――
ようやく某大学の某先生(もちろん数学者)に研究生として指導してもらえる
という話をつけました。
しかし
卒業式の後
彼を呼び出して話をすると,
「数学でやっていく自信がありません」とのこと。
あぁ
そういえば
すぐ上にも『数学で博士に行くのは難しい』て書いていたっけ。
「じゃあ
どうするの?」と訊いたら
「公務員を目指して勉強します」と言うので,
「受かったら
報告してくれ」と言ったら,
「受からなかったら
報告しなくていいんですか」とつぶやいて,
それっきり彼からは何も連絡がない。
あのねェ
『AならばB』から『AでないならばBでない』は結論できないのだよ。
このページを見てたら
連絡してくれー!
 この年は
希望者が6名いたところを1人切って,
5人でやりました。
この年は
希望者が6名いたところを1人切って,
5人でやりました。
上記の院生と同時期にこのゼミを持ったわけですが,
院生が日本語の本を読んでいるのに
4年生が英語というのもどうかと思ったし,
何より01年度の苦労がまだ記憶にあったので
日本語の本で,
上坂 吉則; 量子コンピュータの基礎数理(コロナ社)
を読みました。
最初から 全員就職希望だったので 院に繋げる数学よりも最先端の科学に触れる方が 興味を引くかと思ったのですが, 学生さんは知的好奇心を持ち合わせていないのですね。 近年流行の量子コンピュータの話題を全く知らず, 量子論の『シュレディンガーの猫』とかの話も全然知らないとは驚きです。 2月にこの本を読むと決まったのだし, 数学の本ではないのだから 4月までの間にせめてその手の啓蒙書を 読んでおこうとはしないものでしょうか。
数学の本ではないので
「分からないのは内容が物理だからだ」
という言い訳を用意させたのもまずかった。
じゃあ
数学の質問をしたら答えられるかというと
そんなことは全然無いのだから。
ケッサクだったのは「複素数とはどういうものか」と訊いたときで,
「\(a+ib\) みたいなもの」と答えて
普通はこれでOKなのですが
(要するにその程度のレベルの質問だということです),
更に
「その \(b\) とはどういうものか」と訊いてみると,
「\(\sqrt{-3}\) みたいなもの」なんて答えが返ってくるわけですよ,
これが!
ツッコんでたら
どんどん深みにはまるので,
なるべくツッコまないでおこうと思っていたら
日本語の本だから
学生がただ朗読しているだけでも
僕は内容が理解できるので,
学生が理解していないまま進んでしまっていて
それに気付いたときには,
ずーっと遡らなくてはならなかったりして
結局,
流行の話題を全く理解することなく卒業してしまいました。
就職に関しては
何通かの推薦状を書きましたが,
3人は
東京または佐賀のコンピュータ会社にそれぞれ就職し,
1人は中学の非常勤講師に決まりました。
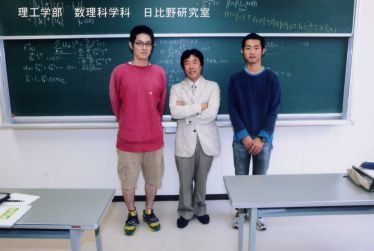 この年はゼミを持たなくてもよかったのですが,
学生の熱意に負けて
ゼミを担当しました。
この年はゼミを持たなくてもよかったのですが,
学生の熱意に負けて
ゼミを担当しました。
一人は自衛隊に入隊し
もう一人は佐賀大学大学院に進学したことからも分かるように,
01年度と同様 二人の数学レベルに差があったのですが,
この年はまともに進んだように思います。
01年度は(03年度も)
メンバー間の仲が親密でなかったのが
良くなかったような気がします。
仲さえ良ければ
(数学の出来が良くなくても)ゼミの雰囲気は
良くなるようです。
最初はW.Feller; An Introduction to Probability Theory and Its Applications Vol.1 John Wiley and Sons Inc 1968の第1章を読んだのですが, 「易しすぎる」と(一人が)言い出したので, 第9章から読むことにしました。 初めは毎週一人ずつやっていたのですが, 「進度が遅いので毎週二人ずつやって欲しい」と(一人が)言うので, 一人目が90分やったらそこから二人目にバトンタッチというやり方でやりました。 2番目の人はどこから自分の発表が始まるか事前に分からないので, 前の人の分から全部準備が必要で 2番目の人に厳しいやり方ですが, それは自分が二人ずつやりたいと言ったんだから。
とにかく二人とも毎週発表しなければならないのですから,
一人目はとばっちり(?)で大変だったでしょうが,
なんとか(飛ばし飛ばしで)14章まで進んで
勉強した気分は満喫したことでしょう。
(本当は15章のMarkov Chainsまで行きたかったのだが)
Fellerの本には
日本語訳があるので
最悪
困ったらそれを参考にすればいいし,
英語の方にあって日本語の方に書いてないことも結構あるので
100%日本語版に頼ってやるわけにもいかなくて,
あくまでも参考書ということで
学生もやりやすかったのだと思います。

 この年は,
4人で行いました。
昨年度のゼミでW.Feller; An Introduction to Probability Theory and Its Applications
Vol.1
John Wiley and Sons Inc
1968を読んでいるときに
読んでいない前の章を参照されることが多かったので
今年度は第2章から飛ばさずに読んでいくことにしました。
しかしこの本は,読んでいない後ろの章を参照したりしているので,
あまり対策にはなっていませんでした。
この年は,
4人で行いました。
昨年度のゼミでW.Feller; An Introduction to Probability Theory and Its Applications
Vol.1
John Wiley and Sons Inc
1968を読んでいるときに
読んでいない前の章を参照されることが多かったので
今年度は第2章から飛ばさずに読んでいくことにしました。
しかしこの本は,読んでいない後ろの章を参照したりしているので,
あまり対策にはなっていませんでした。
第2章が順列組合わせで第5章が条件付確率なので高校の確率みたいですが,
教職志望が多かったこの年には(結果的に)ちょうどよかったと思います。
第3章がランダムウォークの逆正弦法則の話で,ここが一番面白いところですが,
ちょっと難しかったようで毎週19時近くまでかかってしまいました。
それで,後期には日本語版(河田龍夫・卜部舜一訳「確率論とその応用1」紀伊國屋書店)を渡したのですが,
これはよくなかったようです。
前にも書いたように日本語の本だと学生がただ朗読しているだけでも
僕は内容が理解できるので学生が本当に理解できているのかどうかを
確認するために,却ってツッコミが執拗になってしまいました。
メンバーはお互いに仲が良くてゼミの雰囲気は悪くなかったのですが, 数学力に関しても4人とも実に同じくらいのレベルで, だから,一人が解らないときに全員が解らないという状態に よく陥りました。 自分達で協力して考えるという感じではなく 解らなくなったら先生の助け舟待ち,という態度はあまり好ましくありません。
就職に関しては,1人が福岡のコンピュータ会社に,
3人がそれぞれの地元の中学高校の常勤講師に決まりました。
 この年のゼミは,2人でした。
テキストは,Gunnar Blom, Lars Holst, Dennis Sandell;
Problems and Snapshots from the World of Probability,
Springer, 1994.
でした。この本は125の節からなり,それぞれがほぼ個別な話題になっています。
ここから適当に選んで,最終的には54の節を読みました。
この年のゼミは,2人でした。
テキストは,Gunnar Blom, Lars Holst, Dennis Sandell;
Problems and Snapshots from the World of Probability,
Springer, 1994.
でした。この本は125の節からなり,それぞれがほぼ個別な話題になっています。
ここから適当に選んで,最終的には54の節を読みました。
この本の内容は,``離散的な確率''を題材にしていて, 話としては高校生にも分かるようなもので,ネタ本としてはとても面白いです。 しかし,個別の話題がポンポンとあるだけで, 基礎から積み上げていくタイプの本ではないので, そういう意味での数学っぽさは,あまりありませんでした。
05年度からの習慣で,一週に2人ずつ発表させた――つまり
2人ともが毎週発表だった――のですが,
節単位で担当者を決めたため(長さや難易度に不公平さがあったかもしれませんが),
相手の担当分を全然勉強しなくてもよいので,やりにくさはなかったようです。
本のレベルが易しすぎたように僕は感じたのですが,
例えば,等比級数の公式ですぐにできるようなことを,
わざわざ別の計算で長々やって来ていることがよくあったので,
学生たちはそれなりに難しい勉強をした気になっているかもしれません。
実際,大量の計算をして解いた後で易しい別法を見つけたのでそちらを話します,
ってなことも何回かあったし,表面に見えたこと以上に彼らは勉強していたのでしょう。
実は,この本には日本語訳(森真 訳「確率論へようこそ」 シュプリンガー数学リーディングス 第4巻)があるのですが, 学生たちはそれに気づいていなかったようです。 日本語版を朗読されても困るけど,その程度の検索能力がないのも ちょっと寂しかったような…。

 この年のゼミは,3人で,
A.N.Kolmogorov, S.V.Fomin;
Elements of the Theory of Functions and Functional Analysis,
Dover Pub. 1999 (Original Russian edition: Graylock Pr,1957)
の第5-7章,即ち,Lebesgue積分に関する部分を読みました。
この年のゼミは,3人で,
A.N.Kolmogorov, S.V.Fomin;
Elements of the Theory of Functions and Functional Analysis,
Dover Pub. 1999 (Original Russian edition: Graylock Pr,1957)
の第5-7章,即ち,Lebesgue積分に関する部分を読みました。
Lebesgue積分は本学科でも3年生の選択科目にあるのだから,
1回習っていることなので
何とかなるだろうと思ったのですが,
残念ながら
そうではありませんでした。
英語のテキストですが
内容は実にオーソドックスだし
訳本も出ているので,理解できないのはテキストの責任ではありません。
確かに
Lebesgue積分は難しい単元ではあるのですが,
そもそも,可算・非可算も理解していないのでは
測度がわかるわけがありません。
しかも,ヤコビアンも,いや,部分積分すらできないのですから,
もうゼミの間じゅうずっと怒りっぱなしでした。
この年はM1の院生がいたので
オブザーバとして出席してもらっていたのですが,
彼が「学生がいつ泣き出すかと思った」と心配するほどでしたから,
僕の怒りの程度もわかるでしょう。
しかーし,当の学生さんたちは
全然コタえていないのですよ!
この学生たちとは何回も飲みに行ったし,
僕の自宅まで遊びに来るほどで,
ゼミでなければ和気藹々としたものでした。
これはこれで楽しいからいいのですけど,
…どうなんでしょうかねェ。
進路ですが,1人は地元大分のコンピュータ会社に就職し, 1人は佐賀大学大学院に進学しました。
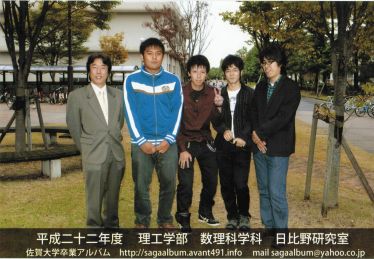
 この年のゼミは,2人で,
ブロム・ホルスト・サンデル; 確率論へようこそ,
シュプリンガー数学リーディングス 第4巻
を読みました。
07年度のこのページを見ていて,日本語訳があるのを知ってて
これを読みたいというので,異例ですが,日本語の本でゼミをしました。
好きな単元を適当に選んで発表してよい,と言ったのですが,
結局,前から順番に読んでいってしまいましたね。
この年は,M2とD1の院生もいたので,
5人でよく飲みに行ったりカラオケに行ったりしました。
この年のゼミは,2人で,
ブロム・ホルスト・サンデル; 確率論へようこそ,
シュプリンガー数学リーディングス 第4巻
を読みました。
07年度のこのページを見ていて,日本語訳があるのを知ってて
これを読みたいというので,異例ですが,日本語の本でゼミをしました。
好きな単元を適当に選んで発表してよい,と言ったのですが,
結局,前から順番に読んでいってしまいましたね。
この年は,M2とD1の院生もいたので,
5人でよく飲みに行ったりカラオケに行ったりしました。
2008年から卒研発表が義務付けられたので,
読んだ中から面白そうなテーマを一つずつ選んでもらい,
それを少し拡張して発表することにしました。
一人は何回も研究室に質問に来たので,
僕の意図した方向に誘導して発表を作り上げることができましたが,
もう一人は直前の発表練習まで姿を現しません。
心配していたのですが,彼は発表練習のときには,
僕が想定していたところまで自力で仕上げてきていました。
彼は就職志望だったのですが,結局最後まで決まらず残念な思いをしました。
ここまで独力でできるんだから,能力はあると思うのですが,
こういう人は自分の実力をアピールできないんですよね。
こまめに顔を出して成果をアピールするのも社会性として大切なことだと思います。

 この年は,3人で,
R.J.Wilson;
Introduction to graph theory,
Pearson.
5th edition 2010
を読みました。
グラフ理論については僕も知らないので,指導するというより
みんなでいろいろ考えながら理解していくという感じでしたが,
対象が具体的なので
それなりに面白かったです。
この年は,3人で,
R.J.Wilson;
Introduction to graph theory,
Pearson.
5th edition 2010
を読みました。
グラフ理論については僕も知らないので,指導するというより
みんなでいろいろ考えながら理解していくという感じでしたが,
対象が具体的なので
それなりに面白かったです。
ここ数年感じていることですが,学生との年齢が離れてきたせいか,
どうも意思疎通がまともにできていないような気がしています。
卒研発表も学生が何をやりたいのかはっきりしないので,結局,僕が考えたままに
発表内容を決めてしまいました。
飲み会を一回も開催しなかったのも,僕から誘わなかったからでしょうか。
下手に誘ってパワハラと言われるのもイヤなので,学生から企画して欲しいんですがね。
でも,夏休みに
一泊二日で神集島へ合宿旅行しました。
他のゼミの学生も一緒に連れて6人で行ったのですが,
このうちの3人が大学院に進学しているので,
この合宿旅行が今後ゼミの恒例行事になるかどうかで,
彼らがこの旅行を本心で楽しんでいたかがわかると思います。
進路に関しては,2人が佐賀大学大学院に進学し,1人は高校の常勤講師になりました。
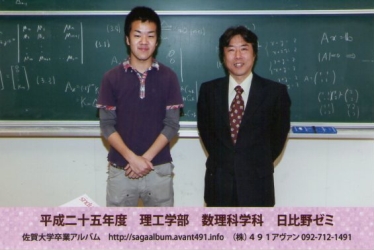
 この年は,1人で,
T.S.Chihara;
An Introduction to Orthogonal Polynomials,
Dover Pub. 2011
を読みました。
この年は,1人で,
T.S.Chihara;
An Introduction to Orthogonal Polynomials,
Dover Pub. 2011
を読みました。
よく考えたら,一人を相手に4年ゼミをするのは初めてでしたね。 彼は就職希望でしたが早々と内定を決めて,「これからゼミに集中します」 ってやる気マンマンだったのですが,それに数学力が伴わなかったようです。 一人だけのゼミでは,詰まってしまうとどうしようもないので, 結局僕が説明することになってしまい, それが続くと,それをアテにして準備がおろそかになる,という悪循環でした。 こういう計算をやってみろ,と言えば,そこそこできるので, それを自分でやってくるだけのことなのですが,それをやってこないのです。 英語の本なので,訳しただけで任務完了!って気分になってしまっているようでした。
この年はM1が二人いたのですが,彼は一留していたので彼らとはもともと同級生です。 同級生にゼミの先輩として臨席されるのも嫌かなって勝手に気を遣って, 修士と学部のゼミには全く接点を持たなかったのですが, やはり,誰かに勉強を見てもらうほうが,良かったかもしれません。 実験系と違って数学は一人でやるものとはよく言われますが, 人は一人だけでは頑張れないものなのです。

 この年は,5人で,
F. Mosteller;
Fifty challenging problems in probability with solutions,
Dover Pub. 1987
を読みました。
この年は,5人で,
F. Mosteller;
Fifty challenging problems in probability with solutions,
Dover Pub. 1987
を読みました。
この本には,56問の確率の問題とその解答が載っています。 しかし,07年や10年に読んだ本とは違って,かなりくだけた本でした。 例えば,11番の問題は
2人に別々に正の整数を一つ言ってもらう。 2人が同じ数字を言ったら賞金がもらえるとしたら,あなたは何の数を言えばよいかというものですが,これが確率の問題というには無理があります。 心理学とかそういう方面ではないでしょうか。
12番の問題もユニークです。
お互いによく知らない二人が,木曜日の正午にニューヨークで待ち合わせをした。 会う場所を決めていないのだが,どこへ行けばよいかというもので, 正解は「エンパイアステートビル」と書いてありますが, どこが数学でしょうか?
ついでに24番の問題も書いてしまおう。
マービンは午後3時から5時のランダムな時間に仕事が終わる。 彼の母親は山の手に住んでおり,恋人は下町に住んでいる。 彼は,どちらか行きの,先に来た方の地下鉄に乗って,着いた方と一緒に夕食を食べる。 彼の母親は,彼がちっとも会いに来ないと文句を言うのだが, 彼はフィフティフィフティだと言う。 しかし,20日間のうち母親と夕食を食べたのは2回だけだった。 なぜでしょう。こうなると,もう数学の問題じゃなくてクイズですね。 蛇足ですが, 山の手行きの地下鉄の本数が少ないとかいう答えではなく, 両方が等しく,例えば10分おきに運行していたとしても, 山の手行きの1分後に下町行きが来れば,そういうことが起こる,というのが解答です。
他の問題も全部こんな感じというわけではないですけど (むしろ特殊な方からベスト3を選んだわけだが), こんな本では数学を勉強するというより, 英語の読み物を楽しむという雰囲気にしかなりません。 もともと誰も大学院には進学しないということだったので これでもいいかなって,それなりに楽しくゼミをしたのですが, 結果的には,就職したのは3人で,2人は佐賀大学大学院へ進学しました。 こんな程度で大学院でやっていけるとおもうなよ!
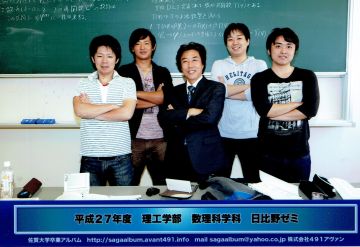
 この年は,4人で,
A. N. Kolmogorov & S. V. Fomin;
Elements of the Theory of Functions and Functional Analysis [Two Volumes in One],
Martino Fine Books
2012
(Original Russian edition: Graylock Pr,1957)
の第3,4章
を読みました。
この年は,4人で,
A. N. Kolmogorov & S. V. Fomin;
Elements of the Theory of Functions and Functional Analysis [Two Volumes in One],
Martino Fine Books
2012
(Original Russian edition: Graylock Pr,1957)
の第3,4章
を読みました。
この本は'08年にもゼミで読んでいて,そのときは第5-7章のルベーグ積分でしたが, 今回は第3,4章ですから,それより前の内容です。 しかし,内容はまさしく「関数解析」です。 関数解析はルベーグ積分の続きで講義されることが多く, ルベーグ積分で脱落してしまった学生は関数解析の話を聴くことがないというのが もったいないと思っていたので, ルベーグ積分なしで関数解析をやるっていうのが この本の良い点だと感じました。 ルベーグ積分アレルギーの学生にも関数解析が理解できるならそれに越したことはありません。
ただ,英語で無限次元を説明されてもイメージが追い付かないのか, 学生は英語を訳すだけで何も理解できていない状態でした。 この内容なら日本語の本でもいくつもあるので, いっそのこと日本語で読んだ方がよかったかもしれません。 しかし,'03年のように理解しないまま朗読されるのも嫌だし,悩ましいです。 適当な日本語の本を参考にして発表の準備をしてくれればいいのですが, そういう無駄な(表面に現れない)努力を学生はしないんですよねぇ。
進路は,1人が生命保険会社に就職し,3人が佐賀大学大学院に進学しました。 大学院入試の面接で,3人とも「ゼミの内容が面白かった」と言ってましたが, とてもそうだとは思えないのですけど本当のところどうなのでしょう?
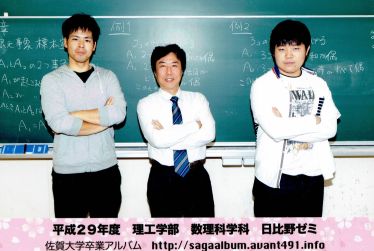
 この年は,2人で,
Y. A. Rozanov & Iu A. Rozanov;
Probability Theory : A Concise Course,
Dover Publications; (1977)
を読みました。
この年は,2人で,
Y. A. Rozanov & Iu A. Rozanov;
Probability Theory : A Concise Course,
Dover Publications; (1977)
を読みました。
目次としては,W.Feller; An Introduction to Probability Theory and Its Applications
のVol.1とほぼ同じですが,ページ数が100ページちょっとしかないので,
1回で3-4ページしか進めなくても
一年でマルコフ連鎖まで行けるのがとても良いです。
内容的にも最低限必要なことはちゃんと押さえてあって,なかなか良い本だと感じました。
しかし,確率論を全く知らない学生にとっては,
簡単な説明だけでどんどん先へ進んでしまうので,
分かりにくいという感想を持ったようでした。
丁寧な説明があると時間がかかるし,なかなか難しいものです。
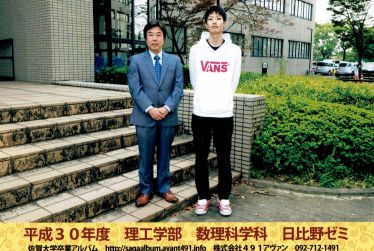
 この年は,1人で
ダイアコニス・グラハム;
数学で織りなすカードマジックのからくり,
共立出版; (2013)
を読みました。
この年は,1人で
ダイアコニス・グラハム;
数学で織りなすカードマジックのからくり,
共立出版; (2013)
を読みました。
数学も英語も得意ではないということだったので,メンバーも一人だけだし, 面白さ優先で数理マジックの本を選んでみました。
この本は最初の方は著者のマジックネタの数学的な発展について書かれていて, 数学的には高度だけれども詳しい証明などはなく, マジックとして見るとそれほど面白いマジックでもないので, 数理マジックの本というイメージとは違いました。 ただ,後半のギルブレスの原理はマジックとして面白かったので, これをテーマに卒研発表をすることにしました。
卒研発表の練習をするには,まずは原稿などそれなりのものが必要なので, その準備ができたら練習しよう,と言って, 1月以降は不定期にゼミを行うことにしたのですが, それっきり全く連絡がありません。 結局,発表の日の3日前にやっと連絡が取れて, \(\TeX\) のインストールすらやっていないということが判明しました。
慌てて\(\TeX\)をインストールし原稿を作ったのですが, 発表当日は肝心のマジックにも失敗するというオチで,最後が締まりませんでした。
卒業に必要な単位が取れていなくて心配が多かったということもあったので, 卒研発表で失敗しても単位を落とすことはないから安心しろ, と言っていたのが裏目に出て,なめられてしまったようです。
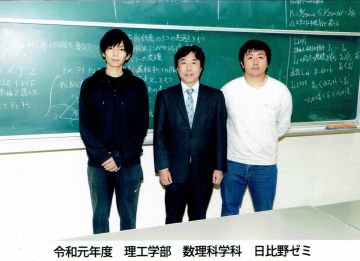
 この年は,2人で
Peter Frankl・前原潤; 幾何学の散歩道―離散・組合せ幾何入門―, 共立出版(1991)
を読みました。
この年は,2人で
Peter Frankl・前原潤; 幾何学の散歩道―離散・組合せ幾何入門―, 共立出版(1991)
を読みました。
昨年日本語の本を読んだことを知っていて,同じように数学も英語も得意でないと臆面もなく言うので, '01年度に読んだ本をもう一度選んでみました。 グラフ理論の本は予備知識なしで読めるのでいいのですが, この先にどう発展させていけばいいのかがわからないので, ただ書いてあることを読むしかありません。 特にこの本は話題が特殊な,特別な場合を扱っているので, そういう印象が強かったです。
ずっと卒研発表の原稿を\(\TeX\) で作成するよう指導していたのですが, この年は学生が僕はofficeが使えますっていうので, パワーポイントで作らせたのですが,複雑な(と言っても,分子に指数がある程度の)数式が 面倒で苦労していました。 WYSIWYGは正確な使い方を理解していなくても使える気になってしまうだけで, 相当なofficeマスターでなければ, 数学の書類を作成するときには 結局は\(\TeX\)をインストールして原稿を作成するほうが 楽だということを学習しました。

 この年は,4人で
B. V. Gnedenko & A. Ya. Khinchin;
An Elementary Introduction to the Theory of Probability
,
Dover Publications 2013 (Original edition 1961)
を読みました。
この年は,4人で
B. V. Gnedenko & A. Ya. Khinchin;
An Elementary Introduction to the Theory of Probability
,
Dover Publications 2013 (Original edition 1961)
を読みました。
'17に読んだRozanovの本と同じようなものだと思って選んだのですが, それよりもずっと初心者向けでした。 しかも,当時のソビエトの風潮が影響しているのか, 例が軍事的なものや農場の収穫に関するものが多くて, 一種独特な雰囲気でした。 でも,内容は易しいので,卒研発表するには足りないと思い, 後半は 池田信行・小倉幸雄・高橋陽一郎・眞鍋昭治郎; 確率論入門I,培風館 (2006) を読みました。
この年はなんといっても新型コロナウィルスの影響で, 学生と会うこともままなりませんでした。 実際彼らと会ったのは, 3月にテキストを決めたときと, 卒業アルバムのゼミ写真を撮るとき, それと,卒業の挨拶に来たとき,の3度だけです。 実際のゼミはzoomを使ってオンラインで行いましたが, 上述の通り内容が易しいので,なんとかやりきれました。
しかし,この形式を今後ずっとやり続けるのは勘弁です。進路は,一人が公務員に,3人が佐賀大学大学院(うち一人は教職大学院)に進学しました。

 この年は,4人で
ダニエル・J・ベルマン;その理屈、証明できますか?,翔泳社(2016)
を読みました。
この年は,4人で
ダニエル・J・ベルマン;その理屈、証明できますか?,翔泳社(2016)
を読みました。
いろんな証明法が並んでいるのではなくて,記号論理の本です。 それも論理学ではなくて,関係とか対応とか順序とか ――分野の名前が分かりませんが―― 基礎的な数学です。 普段,背理法や帰納法を数学的に理屈づけて考えることはあまりしないで, 感覚でやってしまっているので,学生たちにはいい勉強になったと思います。 が,私個人的には何も新しく学んだ感じはありませんでした。 分野の名前もわからないのに,いつどこでどう習ったんだっけな。
日本語訳で読んだこともあって,一冊だけでは1年持たなかったので,
後半は,R.J.ウィルソン;四色問題, 新潮社(2013)
を読みました。
文庫本の啓蒙書では数学のゼミにはならなさそうですが,
そこそこきちんと書いてあったので,証明しながら先に進む感触はありました。
しかし,四色問題をテーマにするなら,やはりグラフ理論として理解するべきだったと思います。
一人が佐賀大学大学院に進学したので,来年はグラフ理論として四色問題を勉強してみるつもりです。

 この年は,5人で
R. A. Wilson; Graphs, Colourings and the Four-Colour Theorem, Oxford Science Pub. (2002)
を読みました。
この年は,5人で
R. A. Wilson; Graphs, Colourings and the Four-Colour Theorem, Oxford Science Pub. (2002)
を読みました。
昨年度の反省を踏まえて,四色問題をグラフ理論の本で読んでみましたが, 確かに数学として書かれていて,読んでて違和感はなかったです。 ただ,そもそも四色問題というのは,最終的にコンピュータを使って証明された,というのがオチになるわけで, 証明を最後まできちんとフォローするということはどうしても無理なわけです。 どうにも最後が締まらない感じで終わってしまったのは仕方がないということでしょう。
進路は,一人が熊本大学の教職大学院,一人が中学の講師,3人が一般企業に就職しました。

 この年は,6人で
M. Gardner; Hexaflexagons, Probability Paradoxes, and the Tower of Hanoi,
Cambridge Univ. Press (2008)
を読みました。
数理パズルで有名なマーチン・ガードナーの本を読んでみたのですが,
話題自体は数学的だしとても面白いのですが,コラムをまとめたものなので,
いかんせん「数学の本」ではありません。
この年は,6人で
M. Gardner; Hexaflexagons, Probability Paradoxes, and the Tower of Hanoi,
Cambridge Univ. Press (2008)
を読みました。
数理パズルで有名なマーチン・ガードナーの本を読んでみたのですが,
話題自体は数学的だしとても面白いのですが,コラムをまとめたものなので,
いかんせん「数学の本」ではありません。
英語の本を読んでいると言っても,今や学生さんは辞書を引くわけでもなく, スマホをかざして翻訳ソフトを起動するだけなので,日本語の本を読んでいるのと同じです (ガードナーの場合は日本語訳の本もあるだろうが)。 2014年のときみたいに,読み物を楽しむという雰囲気にしかなりませんでした。
この内容では卒研発表もできそうにないので,後半は L. E. Dubins & L. J. Savage; How to gamble if you must -- inequalities for stochastic process, McGaw-Hill (1965) の第5章を読んでみたのですが,ガードナーの本に慣れてしまったのか,数学の本は全然読めませんでした。 セミナーは「数学の本」を読む練習だと思っているのですが, 翻訳ソフトがいくら発達しても,これはすぐにはできないことのようです。 結局,発表担当の人だけが僕の準備した通りにしゃべるだけ,というシケた発表になってしまいました。
コロナ禍でしばらく休んでいた神集島合宿も夏に行ったのですが, 当日がちょうど雷雨の日で全く楽しめませんでした。 メンバーはみんな仲良くて体育会系の気のいい奴の集まりでいい雰囲気のゼミだったのに, ちょっとついてない年でした。

 この年は,5人で
A.M.Yaglom & I.M.Yaglom;
Challenging mathematical problems with elementary solutions, Vol.I,
Dover Pub. (1987)
を読みました。
この年は,5人で
A.M.Yaglom & I.M.Yaglom;
Challenging mathematical problems with elementary solutions, Vol.I,
Dover Pub. (1987)
を読みました。
この本は高校生向けの数学の問題とその解答解説が100問載っているもので, 僕としては 大学入試問題のネタ本として興味深かったのですが, いかんせん内容が高校数学程度で,4年生のゼミとしては物足りなかったです。 実際,この本の中からできるだけ難しい問題を選んで卒研で発表したのですが, 他のゼミの学生から「あんな面白いことをどうやって思いついたの?」 などと質問されてしまいました。 全部本に書いてあることだけど,自力でも思いつきそうと思われてしまったのですね。 前年度もそうでしたが,ゼミの本を選ぶときにはいつも学生さんは易しい本を選びたがるのですが, 易しければ何でもいいというものでもないようです。
このメンバーは卒研発表もちゃんと全員で真面目に取り組んだし,
恒例の神集島合宿も好天に恵まれ楽しめました。
いい感じのゼミだったけど,本選びだけが残念でした。
進路については,
1人は佐賀大学大学院に進学し,1人は中学教諭に,3人は企業に就職しました。